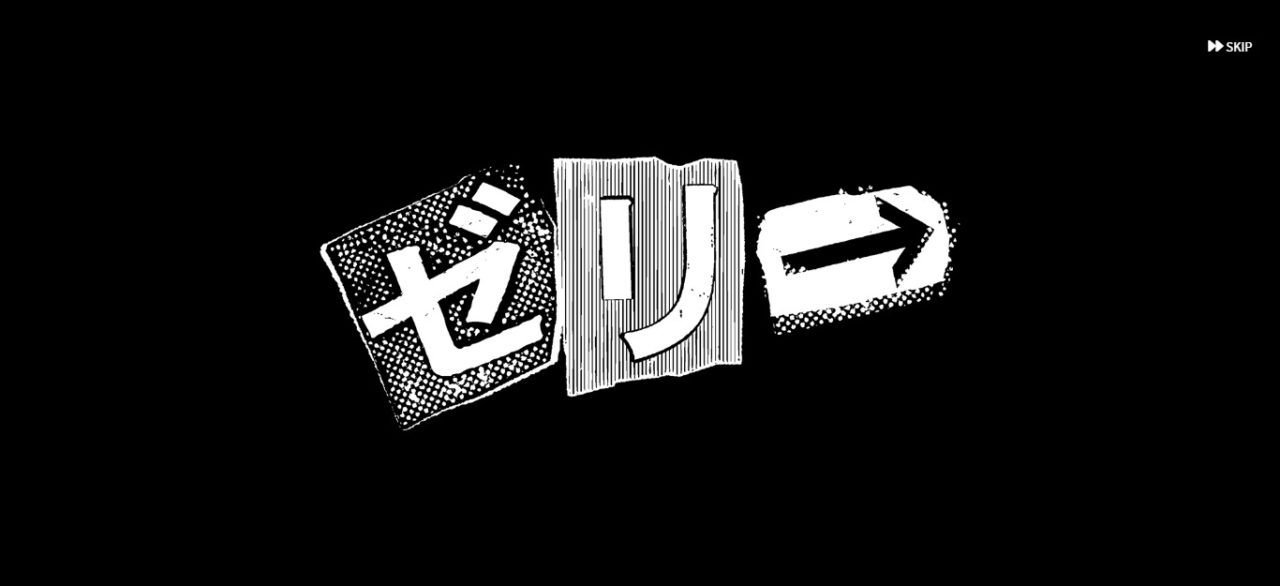単独反抗と銘打って、ゼリ→が2020年内という期間限定で復活を遂げた。
僕はこのサイトでもたびたび紹介しているが、昔からのゼリ→ファンだ。ライブもたくさん行った、音源もすべて持っている、学校へ行く通学時間、バイトへ行く時間、車を運転しているとき、就職して勤めていた会社への通勤時間、何をするときもいつも流れているのはゼリ→の音楽だった。
あの日、突然終わってしまったバンドが10年の時を経て復活を遂げた。
自分の目で見て、聴いて、肌で感じてから文章に起こそうと思っていた。今がそのときだ。
ゼリ→と僕らの本当の距離
中学のとき、おもちゃのピストルが友達同士でかなり流行った。
かっこいいから聴いてみ。
友達同士でCDを貸し借りしたり、兄貴に無断で持ち出してツレに貸している奴までいたり。
「不良」という不良が絶滅した昨今では考えられないかもしれないが、当時のちょっと尖った男子諸君はパンクが大好きだったのだ。つまり僕もその一人だった。
高校に上がって、友達と深夜のカラオケで遊び惚けるときにも、仲間内で大熱唱していたのはゼリ→の曲だった。ゼリ→を知らない友達からはカラオケではじめて聞いて後でこっそりCDを貸してくれ、なんて言われたりして。
人間関係ややりたいこと、将来どういう未来を掴むのか、10代の僕らには悩むことが多すぎて、それでも斜に構えて、かっこつけて、世の中すべてにおびえながら、くだらねえなって強がっていた。
個人的にパンクロックは怒りの音楽だと思っている。ぐちゃぐちゃだった10代の反抗期は世の中の大人が全員汚く見えて、俺たちはこうはならない、って胸に誓って、常にイライラしていた。何かわからない得体のしれない何かに常にムカついていた。
そんな当時の気持ちをパンクロックは吹き飛ばしてくれた。
20代になって、別々の道に行く友達たち。家族のこと、大恋愛をしたこと、ひどく裏切られたこと、ひどく傷ついている人がいること、自分が無力だということを知った。
人生は不思議なもので、頼んでもいないのに次から次に問題を連れてくる。へこたれて、諦めて、ぶっ潰れた夜も、死にたいと思う朝もあった。
自分なんてこの世界に必要のない人間だと思うこともあった。自分がいなければ大切な人がこの先不幸にならなくて済むんじゃないか、なんて考えたこともあった。あのとき、死ぬほど嫌だった「汚ねえ大人」にまさに自分が片足突っ込んでるじゃねえかって、自分がたまらなく嫌いだった、自分をぶっ殺してやりたかった。無力な自分を「なんでてめえはそうなんだ」ってぶん殴ってやりたかった。
当時の腐りかけた男が、それでも腐らずいられたのはゼリ→のおかげだ、なんて言うつもりはない。僕はそんな風に盲目的に狂信的に自分の好きなアーティストを崇拝する、なんてことはしたくない。漫☆画太郎先生以外は。
「死んでも世界は何も変わらない」
このフレーズはきっと誰でも頭で分かっていること。何も変わらない。自分はそんな大きな何かを変えるほどの存在なんかじゃない。そんなことは知っている。分かっている。それでも、そこを認めたくないほど生きていることそれ自体を否定したくなるときもある。
「だから生き抜いて何かを変えてやろう」
何かを変えてやろう、僕の根底にあるのはこの言葉だった。
中学のクソガキだった自分が、あの当時からずっと胸に刺さったままのこの言葉は僕の中のパンクが形成されたものだった。
人間性が形成されたものだった。考えのたどり着く方向が形成されたものだった。反骨精神や反逆心が形成されたものだった。
あらゆるクソみたいな状況はてめえ次第でひっくり返せることを、当時は漠然と、歳をとるにつれて明確に知っていった。
今の自分の、このクソみたいな自分も、「どうせいつか死ぬなら何かを変えてやろう」って、僕の中の僕がひっくり返った瞬間を今でも確かに覚えている。
ゼリ→の音楽にすべて決められたわけじゃない。あくまできっかけを勝手に受け取っただけだ。そのちっぽけなきっかけを時間をかけて育ててきただけだ。
だから、恩がある、という言い方がなんかしっくりくる気がした。
解散前の最後のライブに僕はいた。
解散前の最後のライブが人生で観たライブでぶっちぎりの1位になるほど、衝撃的なライブだった。
これがロックバンドの最終形態なんじゃないかと思えるぐらいかっこよかった。
そのときの衝撃を未だ拭えずに僕は生きてきた。
それが僕にとってのゼリ→だ。
そんなゼリ→の復活。
金儲け?話題集め?くだらねえ理由ではじめた復活なら音源もライブも全部無視するつもりでいた。
ライブの話はツアー中なのでセットリストのネタバレになるのは野暮だ。後日書こう。
「あいつの気持ちを終わらせてやりたかった」
この言葉を聴いてゼリ→をずっと聴いてきてよかったと思った。